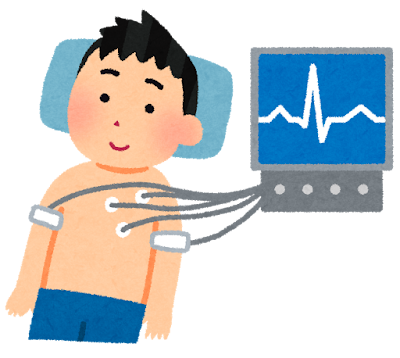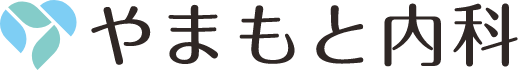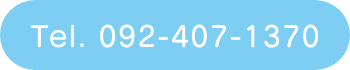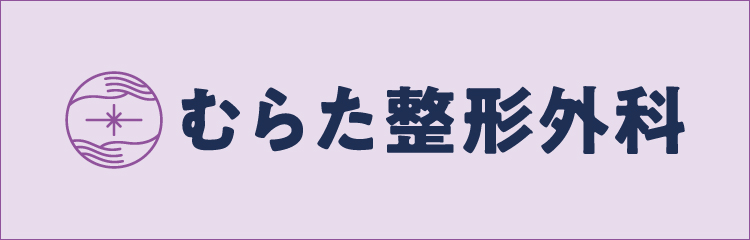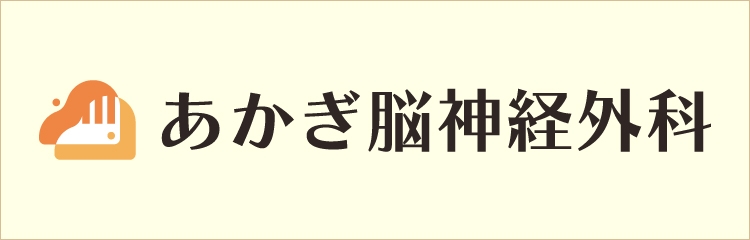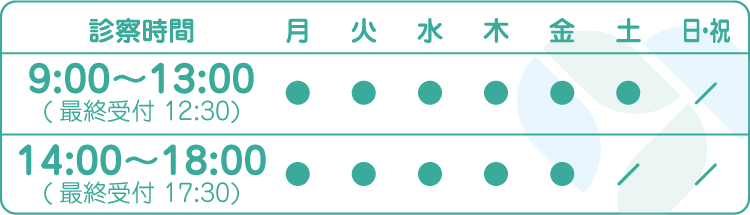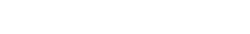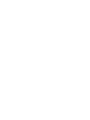*もうすぐ1周年*
早いもので昨年6月に開院し、もう少しで1年が経ちます。
常々、長くお待たせしないようにと心がけておりましたが、特にコロナ禍の第7波・第8波の感染拡大時には、
電話が繋がらない‼ や、ご予約での来院の皆様の診察までに時間がかかり、大変長くお待たせしてしまいました。
又、発熱外来で来院の皆様には、時間を指定して来院して頂いているにも関わらず、時間通りの検査の実施ができず、高熱
の中、お車でお待たせし申し訳ありませんでした。

昨年6月にナースの身長くらいだった待合室の観葉植物がすでに天井まで枝を伸ばし成長しました。
私どもも、少しずつ成長し、皆様が快適に診察を受けられるよう、笑顔かつ迅速・的確な対応に努めてまいります。
何か気になることがありましたら、スタッフにお声かけ下さい。
これからもよろしくお願い致します。
やまもと内科 スタッフ一同
新年度が始まりました
今日から新年度の始まりです。
昼間は少し汗ばむ陽気で、すごしやすい季節になりましたね。
昼と夜の寒暖差が大きく、体調を崩しやすい時期ですので、皆さんも体調管理にお気をつけください。
今年は天気に恵まれ、桜が長く楽しめていますね。
近所の桜並木もまだまだキレイでした🌸
本年度もよろしくお願いします。

*健康は日々の食事の積み重ね*
こんにちは。やまもと内科スタッフです。
世界情勢やエネルギー問題により物価が上がり、私たちの生活を直撃していますね。
私自身、食べ盛りの子どものお腹を満たすため、ついつい安価なパンや麺類に手が伸びがちです。
そんな中、興味深い記事を見ました。
生活費を切り詰めるため、まず行われるのが食費の節約であり、安く空腹を満たすため、炭水化物の摂取が過多になるというのです。
経済力により、野菜摂取量に差ができ、健康格差にもつながるという内容でした。(朝日新聞デジタル)
まさに私の買い物を指摘されている気がしました。
また、そういったパンやめん類は調理が簡単で、一人暮らしの学生さんや、疲れているお父さん・お母さんには強い味方だったりします。
しかしながら、健康は日々の食事の積み重ねにより維持されます。
今日の出費も気になりますが、大切にすべきは、数年後の自分や家族の健康だと考えさせられるものでした。

今宿上町天満宮 鬼すべ
本日は、今宿上町の「鬼すべ」でした。
「鬼すべ」は毎年正月7日に行われる、鬼を祓い1年の無病息災を願う伝統行事です。
私も子どもの頃に何度も見ており、今年は約30年振りに家族を連れて上町天満宮へ行ってきました。
鬼が火の中を駆け抜けるところは特に迫力があり、子どもたちも圧倒されていたようです。
1日でも早くコロナ前のような日常に戻ることを願いつつ、今年も健康で頑張って参ります。
院長


*冬に気を付けるウイルス*
こんにちは、やまもと内科スタッフです。
新年、あけましておめでとうございます。
今年も定期的にちょっとしたお役立ち情報をお届けしていきますね。
さて、新型コロナウイルス第8波真っ只中で、皆さんも大変のことと思います。
コロナウイルスだけでなく、今年は3シーズン振りにインフルエンザも流行期に入りました。
それだけでなく、寒くなると注意を要するのが、ノロウイルス・ロタウイルスです。
コロナ同様に、家庭内で感染拡大させないことが大事です。
今月はその注意事項と具体的対処についてのお話です。
1:タオル・コップ等は共有しないこと
手洗い時のタオルはペーパータオルがいいでしょう。
可能なら紙コップ・紙皿・割りばしを使うことで洗う時の接触を回避できます。
2:とにかく、よく手を洗いましょう
全ての基本ですね。
3:消毒を正しく行い、特にノロ・ロタウイルス感染者からの便・吐物は正しく処理しましょう
便・吐物を処理する時は使い捨てのマスク、手袋を着用します。
汚物の上に新聞紙やキッチンペーパーといった吸水力のある紙をのせ、その上から次亜塩素酸(キッチンハイター)を0.1%に
希釈した次亜塩素酸消毒液をふきかけます。
この時、目に見えない飛散を考え、吐物+1mを意識してペーパーを敷きましょう。(もしかしたら壁もです)
広がらないように外→中へと集めビニール袋へ捨て密閉して破棄します。
1度で取り切れない時はその都度ペーパーをのせ消毒液を散布する作業を繰り返します。
汚物を取り除いた場所に0.02%次亜塩素酸希釈液を散布し10分間浸し、水拭きして終了です。
部屋の換気もしましょう。
4:感染ごみからの飛散を防ぎましょう
ティッシュや感染者の触れたごみはビニール袋に入れ密閉して蓋つきのごみ箱へ捨てます。
その際、アルコール又は、0.02%次亜塩素酸消毒液ふきかけて密閉するとなお良いでしょう。
5:消毒液を正しく使い分け、接触感染を予防しましょう
ドアノブ・手すり・リモコン・洗面台・便座等、家族で共有している場所を消毒します。
ウイルスによって消毒液が異なります。
・インフル・コロナウイルス → アルコール消毒
・ノロ、ロタウイルスの汚物が付着したおむつ・床・便座等 → 0.1%次亜塩素酸消毒液
・ノロ、ロタウイルス感染者が使用したもの、場所 → 0.02%次亜塩素酸消毒液
・ノロ、ロタウイルス感染者が使用した食器、衣類のつけ置き → 0.02%次亜塩素酸消毒液
【次亜塩素酸消毒液の作り方】
0.1%次亜塩素酸消毒液……キッチンハイターの原液を50倍に希釈したもの
例:1ℓの水に20mlのキッチンハイター(ペットボトルのcap4杯分)
002%次亜塩素酸消毒液……キッチンハイターの原液を250倍に希釈したもの
例:1ℓの水に4mlのキッチンハイター(ペットボトルのcap約1杯分)
*注意 消毒液の入っている容器には 【消毒液 飲めません】と大きく表示し子どもの触れない場所に保管してください。
また、日光の当たらない場所に保管し、1週間で使い切るか作り変えましょう。
参考:福岡市保健医療局生活衛生部
食品安全推進課 一部改変
小さなお子様や、高齢者の方に24時間感染予防の行動を守ってもらうことは不可能とおもいます。
換気や空調設備を取り入れながら、可能な限り家族と自分を守りましょう。
ウイルスに負けないよう参考になればと思います。
インフルエンザにはワクチンが有効です。
インフルエンザワクチン接種のご予約は、お電話にてお問い合わせください。
新型コロナウイルスワクチン接種も行っておりますので、福岡市の予約サイトまたはコールセンターよりお申込みください。

新年のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。
皆様、久しぶりの行動制限がないお正月をゆっくり過ごされていますでしょうか。
新型コロナウイルス、インフルエンザ感染には十分お気をつけてお過ごしください。
新年の診療開始は1月5日(木)となります。
本年もよろしくお願いいたします。
院長
2022年 仕事納め
2022年6月の開院から、あっという間に7か月が過ぎました。
たくさんの方々にお力添えをいただき、何とか2022年を無事に終えることができました。
この場をお借りし、心より御礼申し上げます。
本日は午前で診療を終了させていただき、当院スタッフとお隣の野間薬局の薬剤師さんと一緒に心肺蘇生の院内講習を行いました。
日常生活において心肺蘇生を実践する機会はほとんどありません。
だからこそ、いざという時に備えて心臓マッサージやAED(除細動器)の使用方法を経験することはとても大切です。

2023年もスタッフ一同、地域の皆様のお役に立てるよう頑張って参ります。
皆様よいお年をお迎えください。
院長
*年末年始の過ごし方*
こんにちは。
やまもと内科スタッフです。
師走になりました。皆様にとって今年はどんな年だったでしょうか?
年末年始はクリスマス・お正月などの行事が続き、つい食べ過ぎてしまいます。
おせち料理は日持ちがするように塩分が多く使われています。
そのため一般的な1食のおせち料理で1日分の塩分摂取量を超えてしまことがあります。
(男性8g 女性7g/1日塩分摂取量)
*例えば* 塩分量
・数の子 1本 1.0g
・田作り 10尾 0.9g
・かまぼこ 3切れ 1.0g
・昆布巻き 1ケ 0.68g
・煮しめ 100g 2.1g
・お餅入り雑煮 2.0g 合計の塩分摂取量 なんと 7.68g!!
おせち料理は糖分・塩分が多いので、バランスを考えて食べ過ぎにも注意しましょう。
また、年末からお正月にかけてお餅をのどに詰まらせる事故が発生しやすいので、お餅を小さく切る、ゆっくり食べるなどの食べ方に注意しましょう。

見直そう !食習慣
こんにちは、やまもと内科スタッフです。
健康の基本は食習慣です。
過剰に摂取するとかえって健康を損なってしまいます。
バランスの良い食事を心掛けましょう。
主食・主菜・副菜をそろえることで、炭水化物、たんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラル、食物繊維といった体に必要な栄養素を満遍なく取ることができます。
・主食…ごはん・パン・麺など穀物を主な材料とした料理、炭水化物を多く含む
・主菜…肉・魚・卵・大豆を主な材料にした料理、たんぱく質や脂質を多く含む
・副菜…野菜・きのこ・いも・海藻を主な材料とした料理、ビタミン、ミネラル、食物繊維などを多く含む
~食生活を工夫しましょう~
☆食事のリズムを整えましょう☆
・1日3食規則的に食べる
・外食の時は単品とり定食形式のメニューを選ぶ
・寝る前の2時間は食べない
☆食べ過ぎを防止しましょう☆
・食器を小ぶりにする
・汁物やスープを利用して、先にお腹を満たす
・満腹感を感じられるように、よく噛んで食べ、腹八分目を心掛ける
☆夜食や間食を工夫しましょう☆
・アルコールやお菓子など買い置きしない
☆お酒と上手に付き合いましょう☆
・週に2日は休肝日を
・適量を守って、つまみはヘルシーなものを選ぶ
いずれかひとつが1日の適量
日本酒:1合
ビール🍺:中ビン1本
ワイン🍷:グラス2杯
ウィスキー:シングル水割り2杯
焼酎:コップ半分(100ml)
☆塩分は控えましょう☆
・うどんやラーメンのスープは残しましょう
・だし、レモンゆずなどを利用して味付けを工夫する
・しょうゆやソースは『かける』のではなくて『つける』
・香辛料や香味野菜、果物の酸味を取り入れると塩分控えめでもおいしく食べられます
健康の維持・病気の予防のために食習慣を見直してみましょう。

定期健診を受けていますか?
こんにちは、やまもと内科スタッフです。
車は異常なく安全に走ってくれていても、乗り続ければタイヤはすり減り、ある日突然パンクします。
そうならないように車検をして安全走行できるようにタイヤ交換やオイル交換をしますよね。
人の体も点検が必要です。
車のように部品交換できないため、体の健康維持にはもっと気を付ける必要があります。
当院では、特定健診として、
・よかドック
・よかドック30
・後期高齢者健康診査 を受け付けております。
その他の健診として、
・前立腺がん検診
*前立腺がん検診は実施月に指定があり10月と2月のみの実施となります*
・胃がんリスク検査
・大腸がん検診
・B型・C型肝炎ウイルス検査
・風しん抗体検査 も受け付けております。
予約の際、『福岡市○○健診希望』とお伝えください。
自覚症状がないから怖い生活習慣病。
放置していると気づかず進行しタイヤのパンクのように”ある日突然”におそわれるかもしれません。
早期発見・早期治療のため、年1回の健康診断をオススメします。
詳しくはお電話にてお問い合わせください。